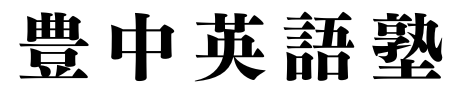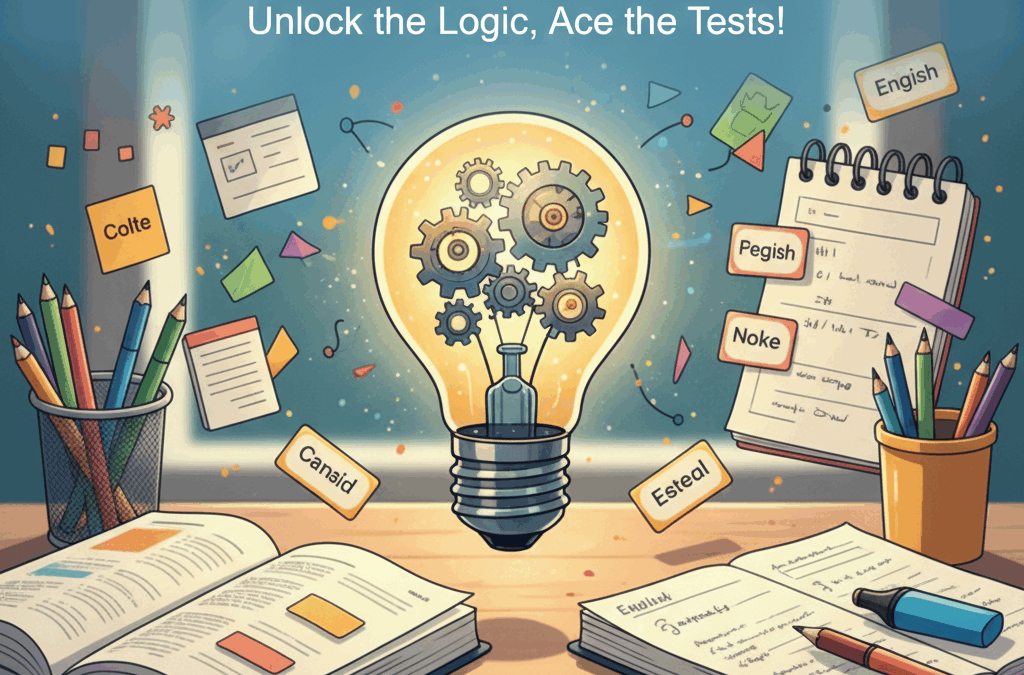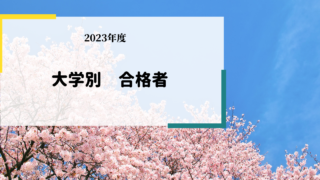こんちは!苦手な英語を得意に!豊中英語塾の飛田です。
塾では生徒たちの理解していないところを改善して文法問題を得点源にしています。
今回は2022年近畿大学のA日程の文法問題を解説します。
- 問題 (13): Mary purchased some flowers she would like ( ) to her grandmother.
- 14. Jack did not consider ( ) to report his failure to his boss.
- 15. The organizers of the event were glad to know ( ) 300 people would join it.
- 16. Ms. Smith’s methods of teaching English are quite different from ( ) of her predecessors.
- 17. The tour guide knows the souvenir shop opens at nine o’clock but does not know ( ) it is open.
- 18. My father told me to do ( ) was right under the circumstances.
- 19. Leon was frustrated because he was made ( ) for over two hours before seeing the doctor.
- まとめ
問題 (13): Mary purchased some flowers she would like ( ) to her grandmother.
【和訳】 メアリーは、祖母に届けてもらいたい花をいくつか購入しました。
【正解】 イ. delivered
【解説】 この問題の核心は、名詞を後ろから修飾する言葉の形と、その**意味上の関係(する側か、される側か)**を見抜くことです。
- まず、some flowers という名詞の後ろにカタマリが続いて、flowers を説明していますね。このように名詞を後ろから修飾(後置修飾)するには、原則として①関係詞節、②不定詞、③分詞のいずれかの形が必要です。
- 次に、動詞 would like は want と同じように、would like O C (OにCの状態になってほしい) という文の形(第5文型)をとります。
- ここで一番大切なのが、目的語(O)である「花」と、補語(C)に入る「届ける」という行為の関係です。花は自分で「届ける」側でしょうか? いいえ、人によって「届けられる」側ですよね。
- このように、OとCの関係が「~される」という受動の関係にある場合、Cの位置には過去分詞を置きます。
- したがって、she would like some flowers **delivered** という形ができます。これは元々 some flowers (which she would like to be) delivered のような関係詞節が省略されて簡潔になった形と捉えることができます。
【他の選択肢】
- ア. deliver (動詞の原形): 名詞の後ろに動詞の原形をそのまま置いて修飾することはできません。「花が届ける」という能動的な意味になってしまう点でも誤りです。
- ウ. delivering (現在分詞): 現在分詞での修飾は「~している」という能動の意味を表します。「花が(何かを)届けている」という意味になり、文脈に合いません。
- エ. delivery (名詞): ここは「届けられる」という分詞が必要です。名詞 delivery を置くと flowers = delivery という同格の関係になり、「届けられる」という動作の意味が消えてしまいます。
【覚えておくと良いティップス】 後置修飾の分詞は「関係代名詞 + be動詞」の省略と考えると、非常に分かりやすくなります。
- a boy running over there = a boy who is running over there (走っている少年) → 能動
- a letter written in English = a letter which was written in English (英語で書かれた手紙) → 受動
この感覚を掴むと、分詞の使い分けで迷わなくなりますよ!
14. Jack did not consider ( ) to report his failure to his boss.
【和訳】 ジャックは、自分の失敗を上司に報告する必要があるとは考えませんでした。
【正解】 ア. it necessary
【解説】 これは、英語の構造上の都合から生まれた重要ルール、仮目的語の it がポイントです。
- 動詞 consider は、consider O C (OをCだと考える) という第5文型の形で非常によく使われます。この文型が成立するには、必ず**目的語(O)**が必要です。
- この文で、本来の目的語(O)は to report his failure to his boss という非常に長い不定詞句です。
- 英語は「頭でっかち」、つまり動詞のすぐ後ろに長々とした目的語が来るのを嫌います。そこで、一旦**「仮の目的語」として it** をOの位置に置き、**「本当の目的語(真目的語)」**である長い to不定詞句を文の最後に回す、というルールが生まれました。
- その結果、consider it C to do … という語順が完成します。C(補語)には形容詞の necessary が入るので、正解は it necessary となります。
【他の選択肢】
- イ. necessary: これでは consider の目的語(O)が欠落してしまい、V O C の文型が成立しません。
- ウ. to be necessary: Cの位置に to be を入れることは可能ですが、やはり仮目的語 it がなければ文が成り立ちません。
- エ. was necessary: Cの位置に was のような時制を持つ動詞の形は置けません。節を入れたいなら consider that S+V… のような形になりますが、今回は不定詞が主役なので不適切です。
【覚えておくと良いティップス】
「仮目的語 it」 を使う動詞はグループで覚えましょう!代表選手は make, find, think, believe, consider (頭文字で MFBTC など) です。
- I found it impossible to finish the work in a day. (その仕事を1日で終えるのは不可能だとわかった)
この形を見たら「お、仮目的語だな!」と即座に反応できるようになると、長文読解も楽になります。
15. The organizers of the event were glad to know ( ) 300 people would join it.
【和訳】 そのイベントの主催者たちは、300人もの人々が参加すると知って喜びました。
【正解】 イ. as many as
【解説】 この問題は、単に数を述べるだけでなく、その数に対する話者の感情、特に**「こんなにたくさん!」という驚きや強調**のニュアンスを表す表現を選ぶことが求められています。
as many as は「~もの多くの」と訳され、まさにその数の多さを強調するのに最適な表現です。主催者が「300人」という数を知って「喜んだ」という文脈から、この数がポジティブな驚きであったことが読み取れます。
【他の選択肢】
- ア. any more than: not any more than… (…しか) のように、否定的な文脈で使われるのが基本です。肯定文のここでは「極性」が合わず不適切です。
- ウ. most of: most of の後ろは原則として the や my といった限定詞がついた名詞が来ます (most of the people など)。most of 300 people という形は文法的に不自然です。
- エ. so much as: not so much as do (~さえしない) のように、これも否定文で使われるのがお約束です。肯定文のここでは使えません。
【覚えておくと良いティップス】 数の強調表現は、セットで対比させて覚えるのが効果的です。
| 表現 | 対象 | 意味 | ニュアンス |
| as many as | 可算名詞 | ~もの(多くの) | 多いことに驚き |
| as few as | 可算名詞 | たった~しか | 少ないことを強調 |
| as much as | 不可算名詞 | ~もの(多くの) | 多いことに驚き |
| as little as | 不可算名詞 | たった~しか | 少ないことを強調 |
16. Ms. Smith’s methods of teaching English are quite different from ( ) of her predecessors.
【和訳】 スミス先生の英語の教え方は、彼女の前任者たちの教え方とはかなり異なります。
【正解】 エ. those
【解説】 これは、一度出た名詞の繰り返しを避けるための代名詞の使い分け問題です。ポイントは「①何を指すか ②単数か複数か ③特定か不特定か」です。
- この文が比較しているのは、Ms. Smith’s **methods** (複数形) と her predecessors’ **methods** (複数形) です。
- 英語では同じ名詞 methods の反復を嫌うため、代名詞で置き換えます。
- of her predecessors のように、後ろから of を伴う語句で修飾され、特定の名詞の繰り返しを避ける場合、代名詞はthat (単数) か those (複数)を使うのが鉄則です。
- 今回は methods という複数名詞を受けているので、those が正解となります。those = the methods の関係です。
【他の選択肢】
- ア. much: 不可算名詞に使うので、可算名詞の methods は受けられません。
- イ. ones: ones も複数の名詞を受けられますが、これは不特定のものを指す場合に主に使われます (例: I lost my old shoes, so I need to buy new ones.)。今回は「前任者たちの」と特定されているため、those の方が遥かに自然で慣用的です。この不特定な物を選ぶ意識が代名詞の攻略ポイントです!
- ウ. others: 「(不特定の)他の人々・物」を指す言葉であり、「方法」という名詞そのものを指し直す機能はありません。
17. The tour guide knows the souvenir shop opens at nine o’clock but does not know ( ) it is open.
【和訳】 そのツアーガイドはお土産屋が9時に開店することは知っていますが、何時まで開いているかは知りません。
【正解】 ウ. how late
【解説】 これは、know の目的語となる間接疑問文を作る問題です。「9時に開店」という開始時点は分かっている。しかし「知らない」のは何か? 文脈から、閉店時間、つまり**「どれくらい遅くまで(何時まで)」開いているか、という終了時点や範囲**を尋ねていると推測できます。
この「どれくらい遅くまで」という程度の範囲を尋ねるのに最適な疑問詞が how + 形容詞/副詞 の形、特に how late です。it is open (開いている) という状態の継続に対して、その終端を問うのにピッタリと適合します。
【他の選択肢】
- ア. at which time: 「どの時点で」という特定の瞬間を尋ねる表現です。「開いている」という継続的な状態とは意味的に合いません。
- イ. by when: by は「~までに」という**期限(デッドライン)**を表します。「いつまでに開いているか」というのは不自然な問いですね。
- エ. what it takes: これは「必要なもの・条件」という意味の名詞節を作るフレーズです。後ろの it is open と文法的に連結できず、意味も全く通りません。
【覚えておくと良いティップス】 how + 副詞/形容詞 のパターンは、様々な「程度」を尋ねるのに使える万能表現です。
- How long will you stay? (期間の長さ)
- How often do you go? (頻度)
- How far is it? (距離)
- How late are you open? (時間の遅さ、終点)
18. My father told me to do ( ) was right under the circumstances.
【和訳】 父は私に、その状況下で(私が)正しいと思うことをするように言いました。
【正解】 エ. what I thought
【解説】 この問題は、2つの文法事項を同時に理解しているかを問う応用問題です。それは①名詞節 what と ②挿入節です。
- まず、…told me to do ( ) の do は他動詞なので、後ろに目的語が必要です。つまり、空欄には**名詞の働きをするカタマリ(名詞節)**が入ります。
- 次に、空欄の後ろを見ると was right と動詞が続いています。ということは、この動詞の主語も必要です。
- ここで登場するのが、先行詞を自分の中に含んだ関係代名詞 what (= the thing which) です。what は、do の目的語になる名詞節を導きつつ、同時にその節の中で was の主語になる、という一人二役をこなせる便利な単語です。
- 基本の形は do **what was right** (正しいことをする) です。
- そこへ I thought (私が思った) を挿入節として加えることで、「私が思うに」という主観的なニュアンスをプラスします。挿入節は、関係詞 what と動詞 was の間に割り込むように入ります。
- したがって、what (I thought) was right が完成します。
【他の選択肢】
- ア. I thought that: do の後ろに置いても「名詞のカタマリ」にならず、文が繋がりません。
- イ. I thought what: what は節の先頭に来るのがルールなので、語順が誤りです。
- ウ. that I thought: that には what のような先行詞を含む用法がないため、「~すること」という意味の名詞節を作れません。
【覚えておくと良いティップス】 「連鎖関係詞」とも呼ばれるこの挿入の形は、what S’ + V’ (think/believe/say…) is/are … のパターンで頻出します。
- This is what they say is the best restaurant in town. (これが、彼らが言うところの、街で一番のレストランです)
- Do what you believe is right. (あなたが正しいと信じることをしなさい)
ウチの生徒たちもよくこの問題に引っかかるんです。しっかり対策しましょう!
19. Leon was frustrated because he was made ( ) for over two hours before seeing the doctor.
【和訳】 レオンは、医者に診てもらう前に2時間以上も待たされて、イライラしていました。
【正解】 イ. to wait
【解説】 英語学習者が最も間違いやすいポイントの一つ、使役動詞の受動態です。ルールは非常にシンプルなので、ここで完全にマスターしましょう。
- 能動態のルール: 使役動詞 make は、make + O + 動詞の原形 の形で「Oに~させる」という意味になります。to がつかない原形不定詞を使うのが特徴です。
- (能動文) The system made him wait. (そのシステムは彼を待たせた)
- 受動態のルール: この能動文を、彼(him)を主語にした受動態にすると、He was made … となります。このとき、能動態では隠れていた(省略されていた)to が復活します!
- (受動文) He was made to wait. (彼は待たされた)
なぜ to が復活するのか? make が受動態になることで、「強制する」という使役動詞の特殊な力が弱まり、一般的な allow O to do や tell O to do と同じように to不定詞を従える形に戻る、とイメージすると覚えやすいです。
いや、そんなん分からない!と思われたら使役動詞(make,have,let)の受け身はtoが必要!それだけ覚えれば大丈夫です。
それとwaitって「待たされる」って日本語で言えるからwaitedで使える!って思う受験生いませんか?
駄目ですよ!文法問題はまずは文法知識で解く!日本語の訳で解くから引っかかるんです。
【他の選択肢】
- ア. have waited: 完了形不定詞を使う理由がありません。
- ウ. wait: これは能動態のときの形です。was made という受動態の後ろでは使えません。
- エ. waited: be動詞 + 過去分詞 (受動態) の後ろに、さらに過去形/過去分詞を続けることはできません。
【覚えておくと良いティップス】 この**「受動態になると to が復活する」ルールは、see や hear などの知覚動詞**でも全く同じです。セットで覚えてしまうのが最強です。
| 動詞の種類 | 能動態 (Active) | 受動態 (Passive) |
| 使役動詞 | They made me do it. | I was made to do it. |
| 知覚動詞 | I saw him enter the building. | He was seen to enter the building. |
まとめ
いかがでしたか?近畿大学は良問が多く受験生が間違えそうな所を的確に聞いてくるので練習問題にピッタリだと思います。文法を覚えて得点源にしましょう。